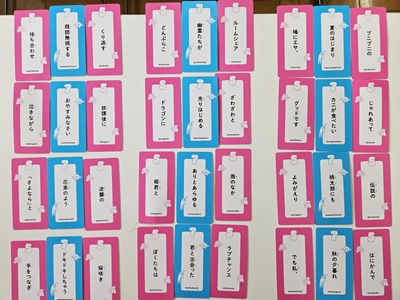トップページ
> とちぎ蔵の街自主夜間中学
> 第33回開催報告
2025.10.9
第33回(2025年10月5日)開催報告
<全体報告>
朝のミーティングで「切手のないおくりものの」の替え歌を歌う。9月28日(日)に開催したシンポジウム「自主夜間中学は何を目指すのか」の交流会に向けてスタッフが準備したものである。どんな「あなた」を想いうかべて、どんな「気持ち」を込めてこの歌をおくるのか。今日は2つの歌詞を取り上げた。「くらのまち あなたへ この歌をとどけよう 不思議な縁で出会ったとちぎ 感謝の意を込めて」(田巻作)。「歩きだすあなたへ この歌をとどけよう どんな時でも笑っていよう エールを込めてこの歌を」(橋本まり作)。次回は3つの歌詞を取りあげる。歌も楽しいが紙芝居も楽しい。何度か披露してもらったが、子どもも大人も、そして日本が難しくても、楽しめているのではないかと感じる。参加者みんなの、じっと見つめて、聞き入る姿が、そして時々聞こえる笑い声がそう連想させる。自分にとって最高傑作は、ほねほねマン。いろいろな物語があるようです。ネットではこんなレビューが載っています。「おもしろいな~!!楽しんで紙芝居を読みたい方にオススメなほねほねマンシリーズです。どこか間が抜けていて憎めない。体が骨だらけなので、ちょっとしたことでバラバラになります。その骨をなんとか組み立てますが、一個抜けていて、アンバランス!!」楽しみが1つ増えた。
とちぎ蔵の街校は昨年10月6日に開校したので、1年が経った!!現在、学習者とスタッフともに毎回10-15人参加しているが、学習者は全員、スタッフの半分以上は開校がきっかけで出会った人たち。開校していなかったら、出会っていなかったのか・・正直、不思議な、しかし、何か必然的?運命的?な縁を感じる。今日は新しく3人(小学生、中学生、社会人)が参加してくれた。これから、どんな人に出会っていくのだろうか。出会いを大切にしていきたい。
当初は月2回、4月から10月までは月3回開講してきたが、11月からは毎週開催することに決定。1回休むと2週間会えなくなってしまうのはとても残念。週に1度必ずこの場所が開かれていることの意味は大きいと思う。東京の公立夜間中学を描いたドキュメンタリー映画「こんばんは」のなかで、見城義和先生が夜間中学へ小走りで向かっていくシーンがある。夜間中学に早く着きたいという想いで、歩いてはいられず、思わず走り出してしまう・・自分もそんな心境だ。自分は車での移動だが、きららの杜に着くまでの約50分間、夜中で出会った様々な人の顔や場面が浮かび、胸が高揚する・・少しスピードを出しすぎかもしれない!!
栃木市は多文化共生推進プランを策定する。有難いことに、策定懇談会のメンバーに加えていただいた。自主夜間中学は年齢も国籍も多様な人々が集う場であり、多文化共生を推進する拠点になりえる。多文化共生推進に向けて自主夜間中学の大事さや役割をアピールしていきたい。(田巻松雄)
<小学生①>
今週の小学生クラスは面白い「ごちゃ混ぜ」な学びの時間となった。ほぼ毎週来ている常連の小学生と幼稚園生の4人のほか、新たにネパールから来た小学校6年生の女の子Aちゃんが加わった。Aちゃんは今年の5月に来日したばかりで、日本語がまだあまり話せない。英語でAちゃんとコミュニケーションを取りながらどう一緒に学ぶかと考えていると、社会人クラスから「英語を勉強したい日本人のFさんを応援できないか?」との応援要請が来た。小学生の部屋に来てもらえれば大丈夫だと答えて、Fさんがやってきた。
さて、どうしようか。大丈夫だと答えた自分は、実はゼロプランなのだ。ふっと、ひらめいた。AちゃんとFさんに互いの学習者になると同時に互いの応援者になるのかどうか、と提案した。Aちゃんは日本語での自己紹介を練習したいので、Fさんにひらがらで自己紹介の文を書くのを教えてもらい、一緒にひらがなの読み練習をして、さらに自己紹介の日本語スピーチの練習を手助けすることをお願いした。そして、Fさんは英語を学びたいので、AちゃんにFさんの英語の自己紹介を一緒に考えて書いて、さらに英語スピーチの練習を手助けすることをお願いした。二人は休まずに真剣に学び合いながら、楽しそうに自己紹介を練習しあった。最初は緊張していたAちゃんの目がキラキラとなり、少し照れているFさんの目には温かみが増した。
AちゃんとFさんの学びが進んでいることにほっとしたところで、今度は中高生クラスから「日本語も英語もあまり話せないペルーの中学生を応援できないか?」との応援要請が来た。スペイン語が全く分からないが、ノーと言わない私の良い(悪い?)癖。同じく小学生の部屋に来てもらえれば大丈夫だと答えて、Bちゃんがやってきた。スマホを取り出し、Google翻訳アプリを開けて、音声機能による翻訳でBちゃんとコミュニケーションを取り始めた。今年の8月に来日したばかりのBちゃんは、会話を練習したいという。ならば、自分が好きなことから話したほうが良いと思って、好きなことを聞いた。
「ラーメンが好き!」とBちゃんが答えた。一番好きなラーメンは、塩ラーメンだという。さらになぜ塩ラーメンが好きなのかを聞いた。うまく答えられないBちゃんに翻訳アプリで「会話をするには、まず何を話したいかを考えることが大切だよ」と伝えた。無料の翻訳アプリは長文の音声を最後までキャッチできないので、Bちゃんにスペイン語で自分が言いたいことを整理してからアプリを使おうと提案した。そこから「あなたが好きなものは?【ラーメン編】」の会話文創作が始まった。会話文をまとめて、Bちゃんに大きな紙に清書してもらって、会話練習をした。
AちゃんとFさん、そしてBちゃんに「みんなの前で発表しようね」と声をかけてみて、拒まなかったので、小学生クラスの前に立ってさらに練習をした。Aちゃんは、やる気満々で楽しそうに練習した。Fさんは照れながら一生懸命に練習した。Bちゃんは少し自信がないものの、精一杯頑張った。常連の4人の小学生と幼稚園生はその近くに行って聞いたり、また自分の遊びや紙芝居づくりに戻ったりして、それぞれの時間を楽しんだ。
3歳児から70代までの幼稚園生、小学生、中学生、社会人の学習者が一つの空間で「ごちゃ混ぜ」になり、それぞれがやっていることも違っていて、「ごちゃ混ぜ」な状態なのに、何だか調和の取れた空間となっていた。例えを言うと、オーケストラが本番前の最後の調音のように、奏者がそれぞれ出したい音を自由に出しているだけなのに、なぜか調和のある力強い音になっていく感じであった。「ごちゃ混ぜ」はいいね。自分も大いに楽しんだ。(鄭安君)
<小学生②>
今回の参加者は6名!でしたが、うち2名は初めての子だったので別メニューでの対応。よって紙芝居作成はいつもの?3名プラスoneで行いました。今日こそ仕上げるぞーーー!と鼻息荒く意気込んでのスタート。相変わらずマイペースの子たちではありましたが、完成まじか・・の雰囲気は感じ取ってくれたようで積極的に参加、比較的スムーズに進んでいきました。思い起こせば8月後半にスタートした紙芝居製作。まずは大まかなストーリーを子どもたちと一緒に考え、次にキャラクターを考え作画に入る。考えたキャラクターを子どもたちなりに表現してくれましたが、描いていくうちにどんどん発想が広がりまた絵の具を使うことが楽しくなり、もはやストーリーなどそっちのけ(汗)でもここは多様性を学び楽しむ所!everything OKなのさ!・・・と2ヶ月近くが経ち何とか95%完成に漕ぎ着けました!!!あとは最終調整と子どもたちの読み上げの練習です。この読み上げにまた一波乱。しっかり力は持っているのに目立つことが嫌いで「絶対に読まない!」と断言している子、気後れせずどんどん読みたいけれど何故か描いてある文字を読まず、自分でストーリー展開してしまう子→おそらくこの子は絵のストーリーをちゃんと把握しているが字を読むのが面倒なので読んでいるかのようなスタイルで自作のストーリーを話しているようだ・・・
残りの5%もなかなかのエネルギーが必要な予感がしますが、でも子どもたちに少しでも達成感や、大勢の人たちの前で披露し楽しんでもらう喜びを感じてもらいたいので、まさにラストスパート!がんばろ〜!
お披露目は10月26日ハロウィンパーティー(これもまた楽しいよ〜)の後、振り返りの時間で!!coming soon!! (橋本まり)
<中高生>
今日は4名の方が参加。その中で、1名の方は初めての参加でした。少し前に来日し、最近県内の中学の第2学年に編入されたというAさんでした。その日は数学と日本語を勉強したいということでした。私が担当することになりました。言葉については英語が良く話せましたので(母国での学校での授業は英語で行われていたのかどうか聞いてみたら、そうではないということでしたが)、日本で編入されたクラスの英語の授業は理解できるということで、これは今後の学校生活で強みになるかなと少し安心しました。
日本語についてもある程度話せるようでした。オンラインで勉強していたということでした。今後、日本語学習というスタンスで日本語を勉強することは勿論重要だと思いますが、他の教科の学習の際や学校生活の中で、案外早く日本語が上達していくのではと感じました。
学校の先生が貸してくれたという数学の問題集を持ってきていました。Aさんが母国で学習した数学よりも編入された学年で現在学習している数学の方が進んでいる様子でした。その日は基礎的な文字式の計算を日本語、英語チャンポンで学習しました。
私たちも嬉しかったことを一つ。学習の途中、スタッフが『中学教科単語帳』(Aさんの母語と日本語が併記)を持ってきてAさんに渡しました。少し見て、返すべきかと聞きますので返さなくていい、あげますと言いましたら嬉しそうににっこりしました。活用してくれると思います。(T)
<社会人>
学習者は10人。全体の支援者は15名ネパール人2名、日本人2名、中国人2名、タイ人1名、フィリピン人1名、ペルー人1名、インド人1名。今回は10名の学習者が参加してくれました。学習が始まるとN4の学習者とB さんが隣の中高生の教室に移動したので社会人クラスは急にガラ空きになってしまった。4人の学習者と6人の支援者がのこった。学習が始まる前にいつものようにKさんに挨拶にいった。固い握手を交わした後に彼の席の隣に腰を下ろした。「今日は1人ですか」と声を掛けると「ひとりです」とやや俯き加減に答えて呉れた。「友達のNさんは来ないのですか」と尋ねたら「来ないです」と弱い笑みを浮かべた。どうして来ないのかと訊ねようとしたがまた同じ答えが返ってくるのが分かっているのでNさんのことはこれ以上訊ねるのを諦めた。すると「Nアパートで寝ています」と突然返してくれた。休みの理由はいらでも考えられる。仕事で疲れてしまったとか。体調がすぐれないからとか。いくらでも考えられる。Kさんはシンポジウムにも参加してくれた。外国人の参加者は彼だけだった。
ミーテングの後に「切手のないおくりもの」をみんなで合唱したら彼も迷いながら声を出していた。今日はいつものトレードマークの帽子をかぶってこなかったのでいつもと違う印象を受けた。何か考え事をしているような陰を感じた。
学習が始まるといつものKさんの張りのある声が聞えてきたので陰が薄れてきたように思った。学習が終わって教室を出ようとしたら彼が手をさし出してきたので固い握手を交わした。陰がすっかり剝がれていた。「次の12日は休みです。19日に待ってます」と肩を ポンと叩くと「わかりました」と笑みをうかべた。
学習が始まるとFさんが1人取り残されていた。彼を支援していたFさんの姿が今日は見えなかった。彼は英語の学習支援をFさんから受けていた。英語の支援者が見つからないのでT先生に声を掛けたら小学生のクラスに移動していった。小学生クラスで支援 を受けていたことが後で分かった。最後のミーテングで今日学んだことを英語で堂々と発表していた。学んだことを直ぐに発表したので驚いた。真剣に学んだ結果ではと受け止めた。同年齢なので励まされた。
今回もNさんの支援をする。彼女は最近タイの人からユーチューブで英語を学んでいると言う。ノートを開いて見せてくれた。アルファベットの隣の文字はタイ語で書いてあった。来春から学悠館に通うことになっているから今から英語を学んでいるという。どうして英語から学ぶのかと疑問に感じた。日本語が先ではと思ったが彼女の考えを最優先することにした。今日もローマ字を習いたいと言うので五十音をローマ字で書く練習を始めた。整ったしっかりとした文字で一字一字ゆっくりノートに埋めていった。
一字一字丁寧に書く姿勢を見ていると本当に学びたいという思いが伝わってきた。まるで写経をしてように映った。文字をゆっくり書くことで精神統一しているのではという気がしてきた。文字を書いている途中で、暫く教室には来られないと口にした。理由を聞くとタイに帰ってくると言う。暫くとは何日ぐらい休むのですかと更に深堀すると 1か月という。
ずっとタイに返ってないから家族や友達に会ってくると満面に笑みを浮かべた。学悠館に入学したら自主夜間教室に通ってくれるか気がかりになってきた。整体院の仕事をしながらの入学だからかなりの負担になるのではと更に気掛りが重なってきた。「今が1番楽しいの」と一か月前に口にしたのを思い出した。整体院をしながら2人の子育てながら やっと今、自由を手に入れて好きなことができるようになったと、少女のように弾んでいた。今日も学ぶ喜びを楽しんでいるように映った。
10時半近くに、母子がやってきた。前回支援したHさんだ。NさんはTさんに支援をしてもらうことにした。Tさんはベテランの支援者だから安心して任せられることができた。直ぐに2人の笑い声が聞こえてきた。
Hさんは今回で3回目になる。今回は挨拶の学習をした。おはようございます。こんにちは。ありがとうございます。げんきですか。とすらすらと読んだ。あまりにすらすらと読めるのでどうしてかなと思ったらひらがなの下に小さくローマ字が書いてあったの でスラスラと読めたのだ。ローマ字を隠すと戸惑ってしまった。ひらがなを読んだり書いたりするのはまだたどたどしい。挨拶の言葉は絵が描いてあるので理解することは出来た。
更に、あさ、ひる、よる、はれ、くもり、あめ、とローマ字で書いてあるのをひらがなに書き直す問題が出てきた。50音表見ながら丁寧に書いていった。今度は数字の読み方が出てきた。イチ、二、サン、シ、ゴ、ロクと続けて行くとスペイン語では何と発音するのか教えてもらうことにした。Ⅰuno,2dos,3tres,4cuatro、8ocho,9nueve,10diez
次に食べ物が出てきた。一番初めにパスターがでてきた。パスターはペルーで人気があるという。そのままで通じるようだ。玉子はhuevo,コーヒーはcafé,スイカはsandía,バナナはplatana,リンゴはmanzana.と教えてくれた。
「先生スペイン語好きですか」と訊ねてきたので素直に「好きになりました」と答えるとうっすら笑みを浮かべた。お互い学び合うことでさらに学習意欲が増してきた。少しづつ彼女のノートにひらがなが書き込まれていくのを見ると嬉しくなってきた。「また来てください」と声を掛けると「ハイ」と返してくれた。
10時過ぎて社会人クラスに女の人が来た。教室には入って来ないで教科書のある部屋に直行した。Ⅰさんが支援をすることになった。様子を窺えに行くと全く日本人と変わらない女性がいた。言葉を交わすと流暢な日本語で答えて呉れて、すぐに名前を書いて くれた。30年以上日本に住んでいるという。30年住んでいても全く日本のことが分からないとリズムよく答えてくれた。特に日本の歴史や地理を学びたいと中学生の社会の教科書をめくり始めた。「日本のことが大好きなので知りたいのです。日本人の皆さんよく勉強していますよね。中国の三国志なんかよく知っているので驚きました。中国人は三国志を あまり知らない人が多いです」と、ハッとするようなことを口にした。三国志は中国の歴史書だ。知っているのは劉備、関羽くらいしかいないので是非、読破したいとおもっている。「日本は中国からたくさんのことを学んできた経緯があります。漢字やいろんな文化を受け入れてきました」「いやいや今や、日本は立派な国です。中国人は日本人からいろんなことを学ばなければなりません」と彼女の言葉には何でも吸収してやろうとする力強さが伝わってきた。彼女に倣って自国の歴史を学び直さなければと改めて自覚した。